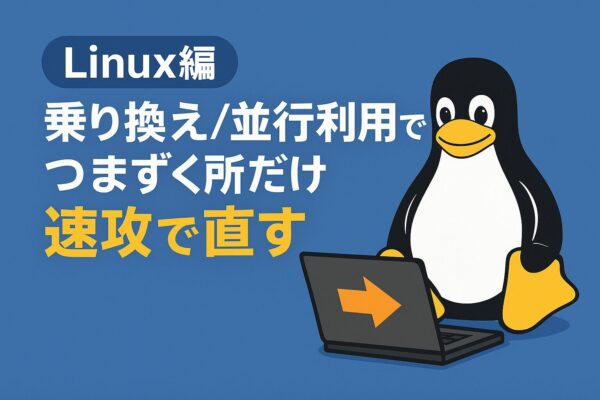
最近では、
- 古いPCをもう一度活用したい
- Windows Updateや動作の重さに疲れてきた
- 開発・サーバー・勉強用にLinuxを触ってみたい
といった理由から、Linuxに興味を持つ方が増えています。
しかし実際に使い始めてみると、
- Wi-Fiにつながらない
- 日本語入力ができない
- USBメモリが認識されない
- 音が出ない
- sudoが使えない
など、最初の数時間で一気に心が折れやすいポイントがいくつもあります。
この記事では、Linux初心者が「乗り換え・並行利用」で本当につまずきやすいポイントだけを厳選し、最短で直すための手順を、できるだけ安全・確実な方法で解説します。
1. Wi-Fiがつながらない・認識しない
Linuxで最も多い初期トラブルが、無線LANが使えない問題です。
よくある原因
- 無線LANチップのドライバが自動で入っていない
- Realtek / Broadcom 製チップで非公式ドライバが必要
- Secure Bootが有効でドライバが読み込まれていない
特に Realtek・Broadcom系 は初心者が最初につまずきやすいです。
対処法①:まずは有線LANで接続する(重要)
Wi-Fiドライバを入れるには、一度ネット接続が必要です。
可能であれば、最初は LANケーブルで接続してください。
対処法②:GUIで「追加のドライバー」を確認(最優先)
まずは一番簡単な方法から試します。
- 設定 → ソフトウェアとアップデート
- 「追加のドライバー」タブを開く
- Wi-Fi関連のドライバー候補が表示されていれば有効化
👉 表示される場合は、これだけで直ることが多いです。
対処法③:無線LANチップを確認する
ターミナルを開き、次を実行します。
lspci | grep -i networkUSB型アダプターの場合:
lsusb表示された メーカー名・型番(Realtek / Broadcom など) を控えておきます。
対処法④:代表的なドライバをインストール
Broadcom系(Ubuntu)
sudo apt update
sudo apt install bcmwl-kernel-source
※「インストールできない」場合は
ソフトウェアとアップデート → 制限付き(restricted) を有効にしてください。
Realtek系(例:RTL8821CE)
sudo apt update
sudo apt install linux-firmware
それでもダメな場合のみ:
sudo apt install rtl8821ce-dkms💡 Secure Bootが有効だとDKMSドライバは読み込まれないことがあります。
BIOSでSecure Bootを無効化すると改善するケースがあります。
再起動して確認
sudo reboot再起動後、Wi-Fi一覧(SSID)が表示されれば成功です。
2. 日本語入力ができない(IMEが動かない)
Linux初期状態では、日本語入力が有効になっていないことがあります。
原因
- 日本語IME(Mozc)が未インストール
- 入力方式(ibus / fcitx)が未設定
Ubuntuでの対処法(定番)
sudo apt install fcitx-mozc
im-config -n fcitx
sudo reboot
再起動後、右上の入力メニューから
「日本語 – Mozc」 を選択します。
入力切替について
- まずは Ctrl + Space
- うまくいかない場合は
設定 → キーボード → ショートカット を確認
※環境差があるため「半角/全角キー」が使えない場合もあります。
3. USBメモリ・外付けHDDが認識しない
Windowsで使っていたUSBやHDDは、
Linuxでそのまま使えない形式のことがあります。
よくある原因
- exFAT / NTFS のサポートが不足
- 自動マウントに失敗している
exFAT(USBメモリ・SDカード)
sudo apt install exfatprogs(Ubuntu 20.04以前)
sudo apt install exfat-fuse exfat-utilsNTFS(外付けHDD)
sudo apt install ntfs-3g認識状況を確認
lsblkUSBのデバイス名(例:/dev/sdb1)を確認後、手動マウントする場合
sudo mkdir -p /mnt/usb
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
※多くの場合、ファイルマネージャでクリックするだけでOKです。
4. 音が出ない・スピーカーが認識しない
原因
- 出力先がHDMIやBluetoothになっている
- 音量管理(PulseAudio / PipeWire)の設定不良
対処法①:出力先を確認
設定 → サウンド を開き、
- 内蔵スピーカー
- HDMI出力
- Bluetooth機器
の中から、正しい出力先を選択します。
対処法②:音量管理ツールを使う
sudo apt install pavucontrol「PulseAudio 音量調整」を起動し、
- 再生タブ
- 出力デバイス
で音量・ミュート状態を確認します。
対処法③:設定をリセット
rm -r ~/.config/pulse
sudo reboot
5. sudoが使えない・パスワードが通らない
よくある誤解
- パスワード入力時は文字が表示されない(正常)
- sudoのパスワードは「ログインユーザーのパスワード」
まず確認すること
- Caps Lockが入っていないか
- 日本語/英語キーボード配列が合っているか
sudo -vこれでエラーが出なければsudo自体は正常です。
💡 Ubuntuでは rootを直接使わずsudo運用が基本 です。
無理に su や root 有効化はしなくてOKです。
6. Windowsとデュアルブートできない
原因
- GRUBがWindowsを検出していない
対処法
sudo os-prober
sudo update-grub
再起動後、Windowsがメニューに表示されるか確認します。
※Windows側で BitLocker有効 の場合、検出されないことがあります。
7. 時計(時刻)がズレる
LinuxとWindowsで時刻管理方式が違うため、ズレが発生します。
対処法(Linux側)
timedatectl set-local-rtc 1 --adjust-system-clockこれでWindowsと同じ時刻になります。
8. apt update でエラーが出る
ディストリ更新直後などに一時的なエラーが出ることがあります。
sudo apt update --allow-releaseinfo-changeそれでも続く場合は、表示されたエラーメッセージに従い公式手順を確認してください
(鍵管理はディストリごとに異なるため、深追いしすぎないのが安全です)。
[PR] Linux乗り換えが一気に楽になる定番アイテム
- USBメモリ(16〜32GB):起動USB作成に必須
- Bluetoothアダプター:マウス/イヤホンの接続トラブル対策
- HDMIケーブル:外部モニター切り分けに便利
- エアダスター:USB端子の接触不良対策に
まとめ
Linuxは、
最初の数個の壁を越えるだけで一気に快適になるOSです。
特に重要なのは、
- Wi-Fi
- 日本語入力
- 音
- USB
この4点を最初に整えること。
慣れてくると、Linuxは
軽く・速く・トラブルに強い心強い相棒になります。
つまずいたら、焦らずこの記事を見返して、
最短ルートで「快適なLinux環境」を取り戻してください。
おすすめ関連記事
・仮想化ディスク、結局どれが最適?Linux/VBox/VMwareの違いをわかりやすく解説


