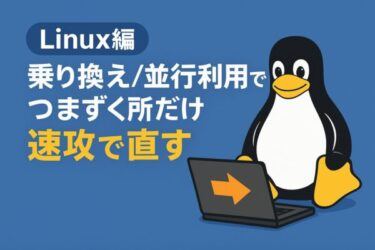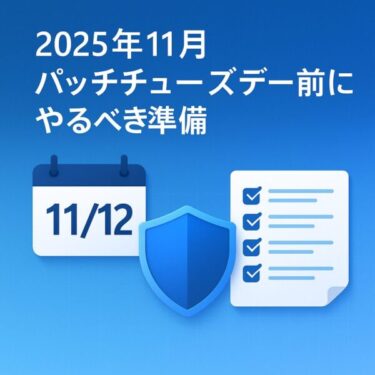はじめに
はじめてLinuxを使うとき、最初に戸惑うのが
「Wi-Fiがつながらない」「文字が打てない」「音が出ない」などの“最初の壁”です。
コマンドを打つのは怖い…という方も大丈夫。
ここではマウス操作(GUI)だけでできる直し方を、できるだけわかりやすく紹介します。
Ubuntu・Linux Mint・Zorin OSなど、一般的なデスクトップ環境で同じように使えます。

1. Wi-Fiがつながらない・表示されないとき
手順1
Wi-Fiスイッチを確認
ノートPCの機種によっては、Wi-FiのON/OFFボタンやキー(Fn+F2など)が付いています。
まずはこれが「ON」になっているか確認します。
💡ヒント:Windows時代に“飛行機マーク”を押していたキーがあれば、それがWi-Fiスイッチのことが多いです。
手順2
「設定」→「ネットワーク」を開く
- 画面右上(または右下)のWi-Fiマークをクリック
- 「設定を開く」または「ネットワーク設定」を選ぶ
- 「Wi-Fi」がオンになっているか確認
- SSID(自宅のWi-Fi名)が表示されたらクリック→パスワードを入力
⚠️「Wi-Fiアダプターが見つかりません」と出る場合
→ お使いのPCに合うドライバが自動インストールされていない状態です。
USBケーブルで一時的に有線接続すれば、再起動後に自動認識することもあります。
2. 日本語入力ができない(半角/全角キーが反応しない)
手順1:地域と言語設定
「設定」→「地域と言語」を開く
- スタートメニュー(左下のマーク)→「設定」
- 「地域と言語」または「言語サポート」を開く
- 「入力ソースを追加」をクリック
- 「Japanese(日本語)」→「Mozc」または「Japanese (Anthy)」を選択
手順2:入力切り替えを確認
右上に「A」や「あ」と書かれたアイコンがあればOK。
クリックで「日本語入力ON/OFF」を切り替えられます。
または、半角/全角キーまたは Ctrl + Space でも切り替え可能です。
💡Mozc(もずく)とは?
Google日本語入力のLinux版です。辞書精度が高く、日本語入力がスムーズになります。
3. 音が出ない・スピーカーが認識されない
手順1:正しい出力先選択
「設定」→「サウンド」を開く
- スタートメニュー →「設定」
- 「サウンド」または「音量設定」を開く
- 「出力」タブで「スピーカー」「HDMI出力」「Bluetoothイヤホン」など、正しい出力先を選択
手順2:音量とミュート設定を確認
- 音量スライダーが0になっていないか
- 「ミュート」ボタンが押されていないか
- 音量を少し上げて再生をテスト
💡 HDMIケーブルで外部モニターにつなぐと、音が“モニター側”に切り替わることがあります。
この場合は「出力先」を手動で“内蔵スピーカー”に戻せばOKです。
4. USBメモリや外付けHDDが開かない
手順1:差し込み直してみる
USBポートを一度抜いて、別のポートに挿し直します。
PC側が認識していれば、数秒後に画面右下に通知が出て自動的に開きます。
手順2:手動で開く
- スタートメニュー →「ファイル」または「ファイルマネージャ」
- 左側に「USBドライブ」や「外付けドライブ」と表示されていればクリック
💡「開けません」と表示された場合
→ Windowsで使っていたNTFSやexFAT形式でも、Ubuntu 22.04以降ならほとんどそのまま開けます。
それでも無理な場合は、別のUSBポートを試すか、再起動してみましょう。
【スポンサーリンク】
Linuxの初期トラブルを“最短”で解消する基本ツール
※ 本リンクはAmazonアソシエイトを利用しています(JP/DE: kimiyoyade-21、US: kimiyoyaus-20)。
5. 音が出ない・USBも反応しない・画面が固まる(再起動時)
手順1:いったん電源を落とす
- 電源ボタンを長押し(5〜10秒)
- 完全に電源が落ちたら、再度電源を入れる
再起動で設定が反映され、音やデバイスが復活することがあります。
手順2:ログインして再確認
起動後、「設定 → サウンド」や「設定 → ネットワーク」で再チェック。
多くのLinuxでは、再起動で自動的にハードウェアを再認識します。
6. WindowsとのデュアルブートでLinuxが起動しない
手順1:起動時にOS選択画面が出ない
BIOS(起動時の黒い画面)で、Boot ModeがUEFIになっているか確認します。
- 電源ON直後に F2 や Del キーを押す
- 「Boot」または「起動順序」の設定を開く
- 「ubuntu」「grub」「Windows Boot Manager」などが並んでいればOK
- 「ubuntu」を一番上に移動して保存(F10キーなど)
手順2:Linuxが起動しない場合の応急処置
USBメモリに作ったLinuxインストールメディアを挿して、
「試してみる(Try Ubuntu)」を選び、修復ツールを起動します。
そこからGRUBブートローダーの再構築も可能です。
💡 デュアルブート構成では、Windowsアップデート後にLinuxの起動順が変わることがあります。
BIOSで起動順を直せばほとんどの場合解決します。
Linux初心者のよくあるトラブルと解決の早見表
| 症状 | まず試す操作(マウスだけ) | 改善しない場合 |
|---|---|---|
| Wi-Fiがつながらない | 右上のWi-Fiアイコン→SSID選択→パスワード入力 | 再起動/LAN接続でドライバ自動認識を確認 |
| 日本語が入力できない | 「設定→地域と言語→入力ソースを追加」→Mozcを選択 | 再起動して「半角/全角キー」で切替 |
| 音が出ない | 「設定→サウンド→出力デバイス」で正しいスピーカーを選択 | Bluetooth機器をオフ/再起動 |
| USBが開かない | ファイルマネージャで左の一覧からUSBをクリック | 別ポートに挿す/再起動 |
| 起動しない(デュアルブート) | BIOSで「ubuntu」を起動順の一番上に変更 | Linuxインストールメディアで修復起動 |
まとめ
Linuxは、最初の設定さえ整えばとても安定して動作します。
今回紹介したように、設定画面(GUI)だけでも多くの不具合は解消可能です。
もしそれでも直らないときは、
詳しい手順をコマンド付きで紹介している別記事👇
「【Linuxトラブル最短修復大全(上級編)】Wi-Fi/日本語入力/音/起動をコマンドで直す」
を参考にしてみてください。
Linuxは、最初の数日は「難しそう」と感じるかもしれません。
でも、設定や再起動を一つずつ試すだけで、ちゃんと応えてくれるOSです。
焦らず、「1つずつ動くようになっていく楽しさ」を感じながら進めましょう。
それが、Linuxとのいちばん良い付き合い方だと思っています。
おすすめ関連記事