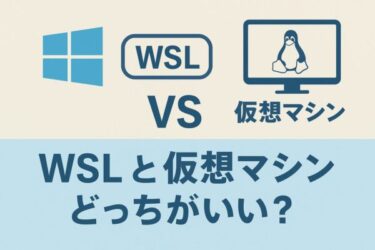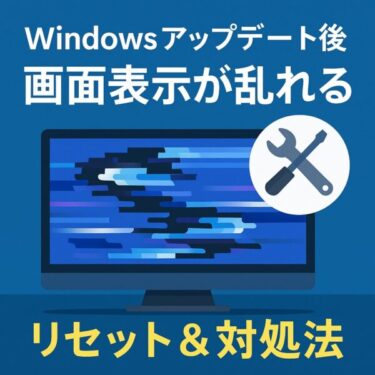「仮想マシンなら隔離されてるし、ウイルス対策なんていらないんじゃない?」
そんなふうに思ったことはありませんか?
たしかに、仮想マシン(VM:Virtual Machine)はホストPC(実際に使っているPC)とは独立した環境に見えます。しかし、だからといって 絶対にウイルス対策が不要 とは言い切れないのです。
この記事では、仮想マシンの仕組みとリスクを踏まえながら、「ウイルス対策が必要か?」についてわかりやすく解説していきます。
そもそも仮想マシンとは?
仮想マシンとは、物理的なPC(ホストPC)の中に、ソフトウェアで作った「もうひとつのPC環境」のことです。
たとえば、Windows PCの中にLinuxを動かしたり、逆にMacの中にWindowsを動かしたりできます。
仮想マシンの特徴は、ホストPCとは別の独立した環境 です。
たとえ仮想マシン内でトラブルが起きても、通常ならホストPCへの直接的な影響は少ないとされています。
仮想マシンにもウイルス感染リスクはある!
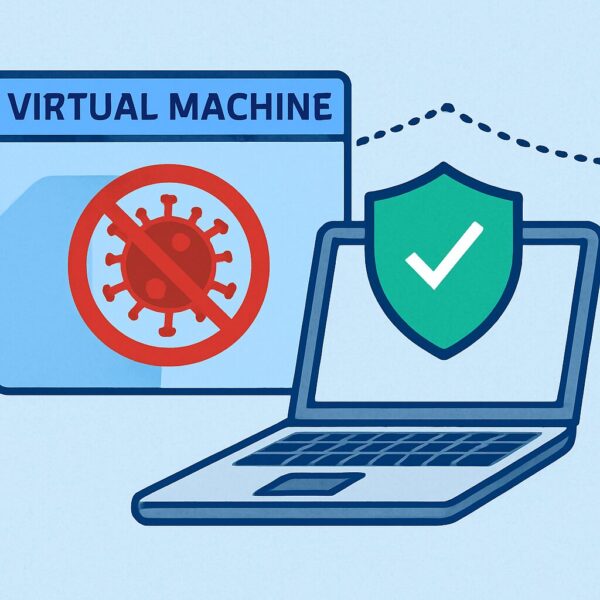
ここがポイントですが、仮想マシンも通常のPCと同じくウイルス感染のリスクがあります。
たとえば…
- 仮想マシン内で怪しいサイトにアクセスしてしまった
- 仮想マシン内でウイルス付きファイルを開いてしまった
- 仮想マシンとホストPCの間で「共有フォルダ」を設定していた
こんなケースでは、仮想マシンだけでなく、ホストPCにまでウイルスが広がる可能性 がゼロではありません。
特に「共有フォルダ」は要注意!
ホストPCと仮想マシンの間でファイルをやりとりできる便利な機能ですが、もし仮想マシンでウイルスに感染したファイルをホスト側に移してしまったら…?
結果的にホストPCも感染してしまう危険 があるのです。
仮想マシンでウイルス対策ソフトは必要?
結論から言うと、
仮想マシンでもウイルス対策ソフトは入れておいたほうが安心です!
理由は以下の通りです。
理由1:仮想マシン内での感染を防げる
たとえホストPCが守られていても、仮想マシン内でトラブルが起きれば、作業環境が壊れてしまいます。
大事なデータが仮想マシンにあるなら、そちらも守らなければ意味がありません。
理由2:ホストPCへの感染リスクを減らせる
仮想マシンとホストPCをつなぐ共有フォルダや、クリップボードの共有機能を使っている場合、感染リスクが生まれます。
仮想マシン内でウイルス対策をしておけば、ホストPCにウイルスが侵入するリスクを最小限に抑える ことができます。
理由3:安全なテスト環境を維持できる
仮想マシンは「怪しいソフトを試す」「未知のファイルを開く」など、リスクの高い作業に使うことも多いですよね。
だからこそ、仮想マシン内でもきちんと守っておくべきです。
仮想マシンのウイルス対策、どうすればいい?
基本的には、仮想マシン内に通常のPCと同じようにウイルス対策ソフトを入れるだけでOKです。
- Windowsの仮想マシンなら「Windows Defender」を有効に!
- Linuxの仮想マシンなら「ClamAV」などを導入
- さらに安全を求めるなら有料のウイルス対策ソフトを入れるのもアリ
>また、次のような設定も意識するとさらに安全です。
- 共有フォルダ機能は必要最小限にする
- クリップボード共有も本当に必要な時だけ
- 仮想マシンのスナップショット(バックアップ)を定期的に取る
万が一ウイルスに感染しても、スナップショットからすぐに元の状態に戻せるので安心です!
まとめ:仮想マシンでもウイルス対策は必要!
仮想マシンは確かに「隔離された環境」ですが、絶対に安全というわけではありません。
特に、ホストPCと仮想マシンが何らかの方法でつながっている場合、ウイルス感染が拡大するリスクも十分にあります。だからこそ、仮想マシンにもウイルス対策ソフトを入れることをおすすめします!
「仮想環境だから大丈夫」と油断せず、しっかり守って、安全な作業環境を維持しましょう!
関連記事