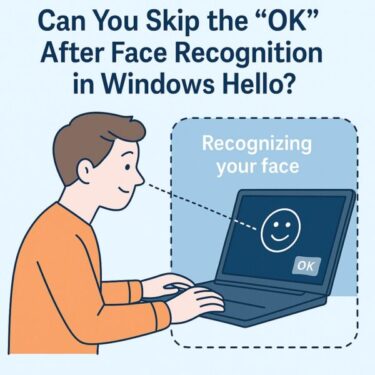電源を入れると「ファイルが壊れているため Windows を起動できませんでした」などのメッセージが出て、先へ進めない――そんな起動トラブルに困っていませんか?
この症状は、起動に必要なファイルやブート構成データ(BCD)の破損、ストレージの異常、更新中断などが原因で起こります。
本記事では、スタートアップ修復 → 更新のアンインストール/復元 → セーフモード → ディスクチェック(chkdsk) → BCD/EFIの修復(bcdboot中心) → オフラインSFC/DISMの順で、データを消さずに復旧を試す手順を解説します。
- 1 原因を知ろう
- 2 ステップ別|復旧の方法
- 3 最終手段:データ救出と再インストール
- 4 再発防止のために
- 5 おわりに
原因を知ろう
このエラーは、Windowsの起動に必要なファイルが破損していたり、消えてしまったときに発生します。
- 強制終了や電源断によるファイル破損
- ウイルス感染
- ハードディスクやSSDの故障
- Windowsアップデート中のエラー
このようなエラーが発生するきっかけとして、意外と見落とされがちなのが「バッテリー切れ」や「電源ケーブルの抜け」による突然のシャットダウンです。
たとえば、Windowsがアップデート中やファイルの読み書き中に電源が切れてしまうと、システムファイルが中途半端な状態で保存されてしまい、起動時に必要な情報が読み込めなくなります。
また、古いハードディスクでは、物理的に読み取れないセクタ(不良セクタ)が原因となるケースもあります。SSDでも寿命が近づくと突然ファイル破損が起きることがあるため、使用年数にも注意が必要です。
では、実際にどう対応していけばよいのか、順を追って解説していきます。
ステップ別|復旧の方法
ステップ①:外付け機器を外して再起動
USBメモリ、外付けHDD、SDカード、プリンターなどをいったん外し、再起動します。
起動順の誤検出で、Windowsではなく別デバイスを起動しようとして止まることがあります。
ステップ②:スタートアップ修復を試す
※自動で直る可能性が高いといわれている方法です。
回復環境(自動修復)に入れたら、
トラブルシューティング → 詳細オプション → スタートアップ修復 を実行します。
ここで直るケースは意外と多いです。
ステップ③:更新のアンインストール/システムの復元
※起動直後から壊れた場合に強い方法です。
回復環境で次を順に試します。
- 更新プログラムのアンインストール(最新の品質更新/機能更新)
- システムの復元(復元ポイントがある場合)
ステップ④:ディスクチェック(chkdsk)で読み取り不良を潰す
回復環境の コマンドプロンプト で実行します。
①まず Windows のドライブ文字を確認(C:とは限りません)
②dir C:\Windows → ダメなら dir D:\Windows…で探します。
③見つかった文字を X: として、次を実行chkdsk X: /f /r
※時間がかかりますが、ストレージ不調が絡むケースに有効です。
ステップ⑤:UEFI/GPTの基本修復(bcdbootでEFI/BCDを作り直す)
①コマンドプロンプトで以下を実行します。(EFIをS:に割り当てます)
diskpartlist volume(FAT32で100〜300MB前後がEFIのことが多い)select volume EFIの番号assign letter=Sexit
②次に Windows の場所(X:\Windows)を確認したうえで実行してください。bcdboot X:\Windows /l ja-JP /s S: /f UEFI
ステップ⑥:オフラインSFC/DISM(システムファイル修復)
Windowsのドライブ文字をX:にして実行します。
sfc /scannow /offbootdir=X:\ /offwindir=X:\WindowsDISM /Image:X:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth
(補足)bootrecは“レガシーBIOS/MBRの場合のみ”
古いPC(Legacy/MBR)だけ、次が効くことがあります。bootrec /fixmbrbootrec /rebuildbcd
※UEFI機では上の bcdboot を優先してください。

インストールメディアの作成手順
- Microsoft公式サイトで「Media Creation Tool」をダウンロード
公式リンク▶︎Windows 11用Media Creation Tool(Microsoft公式) - 起動して「別のPCのインストールメディアを作成する」を選択
- USBメモリ(8GB以上)を選び、作成開始
USBで壊れたPCを起動する方法
- USBをPCに挿し、電源を入れて [F12] や [Del] を連打
- BIOS/UEFI設定から「USB起動」に変更し保存
- 「Windowsのインストール」画面が出たら、「コンピューターを修復する」を選択
ここから「スタートアップ修復」や「コマンドプロンプト」で復旧操作が可能です。
修復できない場合に多い落とし穴
インストールメディアを使っても修復できない場合、以下のような点が原因で失敗していることがあります。
| 落とし穴 | チェックポイント |
|---|---|
| USBメディア作成ミス | 8GB以上、正しいフォーマット形式か |
| 起動モードの不一致 | UEFI起動でUSBを選べているか/Legacyになっていないか |
| アーキテクチャ不一致 | 32bit/64bitの確認 |
| 物理故障 | CrystalDiskInfoなどで状態確認 |
これらに該当する場合は、別のUSBを使ってメディアを作り直したり、BIOS設定を変更してみることで解決できることがあります。
UEFI/GPTの基本修復:bcdboot でBCD/EFIを再構築
- コマンド プロンプトで
diskpart→list volumeで EFI パーティション(FAT32/100〜300MB 目安)を確認 - EFIに一時ドライブ文字を割り当て
diskpart
list volume
select volume EFIの番号
assign letter=S
exit
bcdboot C:\Windows /l ja-JP /s S: /f UEFI
※ Windows のドライブ文字が C: でない場合は適宜読み替えてください。レガシーBIOS/MBR 環境のみ fixmbr / fixboot が有効です。
オフライン SFC / DISM(起動できない場合)
sfc /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=C:\Windows
DISM /Image:C:\ /Cleanup-Image /RestoreHealth
※ 時間がかかることがあります。完了後に再起動し、起動可否を確認してください。
最終手段:データ救出と再インストール
どうしても復旧できない場合は、外付けHDDやUSBメモリでデータを救出し、Windowsをクリーンインストールする方法を検討しましょう。
※データが非常に重要な場合は、専門業者への相談もおすすめです。
再発防止のために
- 定期的にバックアップを取る
- PCの電源を突然切らない
- 健康状態チェックツール(CrystalDiskInfoなど)を活用
- 信頼できるセキュリティ対策ソフトを導入
このような起動トラブルは、一度復旧しても再発することがあります。だからこそ、「日々の使い方」こそが最も効果的な予防策になります。
たとえば、電源を切るときには必ず「シャットダウン」を選ぶこと。アップデート中に電源を切らないこと。そして、異音がする・動作が重いといった兆候を見逃さず、早めに対処することが重要です。
普段からちょっとした注意を心がけることで、大切なデータや作業環境を守ることができます。
バックアップ方法
突然のトラブルに備えるなら、日頃からバックアップをとっておくことが何よりの対策です。
- 外付けHDDやSSD:大容量のデータを高速に保存でき、写真や動画のバックアップに最適
- USBメモリ:重要なファイルだけをこまめに保存しておくのに便利
- クラウドストレージ(OneDrive、Google Driveなど):インターネット経由でどこでもアクセス可能
バックアップは「1つだけでなく、複数の手段を組み合わせる」のが鉄則です。
最近の傾向と注意点
Windows Updateの途中で電源断が起きたり、ストレージの不調が重なると、起動に必要な情報が読み込めなくなることがあります。アップデート前にバックアップ、そして回復用USB(インストールメディア)の作成を習慣にしておくと、復旧が一気に楽になります。
▶ インストールメディア用に最適なUSBメモリは、8GB以上の容量がおすすめです。USB 3.0対応なら作業も高速に進みます。復旧や再インストールの際には、USBメモリが必須です。信頼性が高く高速なUSB 3.0対応製品を1本持っておくと、いざというときに安心です。
[スポンサーリンク]
インストールUSBの作成・バックアップに必須です。迷ったらこの2つから。
今後のトラブルを防ぐためにも、日ごろからの備えを習慣化しておきましょう。
おわりに
「ファイルが壊れているためWindowsを起動できませんでした」というメッセージが出ても、復旧の可能性は十分あります。ひとつひとつの手順を落ち着いて試してみてください。
また、自分での復旧が難しい方は、プロに相談するのも手です。
【スポンサーリンク】
訪問・電話・リモートなど柔軟に対応。初期費用0円プランがある
全国対応パソコン修理・復旧サポートはこちらです(G・O・G)もおすすめです。
この記事が少しでもお役に立てば幸いです。
【関連記事】