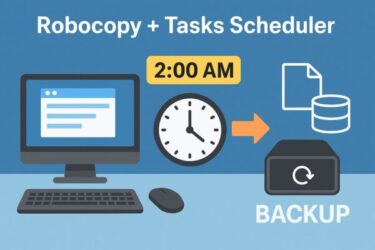「今のサーバー、いつまで安全?」
「2019と2022の違いは?」
「更新停止後は何が起きる?」
——管理者が真っ先に知っておくべき“期限と行動”を、実務目線で簡潔にまとめます。
- Windows Server 2019:メインストリームは2024年1月9日で終了、延長サポートは2029年1月9日まで。以降はセキュリティ更新なし(ESUの提供は現時点で公式アナウンスなし)。
- Windows Server 2022:メインストリームは2026年10月13日まで、延長サポートは2031年10月14日まで。
- Windows Server(LTSC)は“5年+5年”が基本(メイン5年+延長5年)。運用方針はこの原則で設計するのが安全。
※Microsoftのライフサイクル日付は米国太平洋時間(PT)表記。日本時間では翌日になることがあります。
LTSCの考え方
Windows Server の長期サービスチャネル(LTSC)はメイン5年+延長5年の合計10年。延長期間中は機能追加なし・セキュリティ修正中心という前提で、更改計画(ハード/OS/アプリ互換検証)を逆算します。
注:ESU(Extended Security Updates)はサポート切れ製品に限定的に提供される有料の最終手段ですが、対象や条件は製品ごとに告知されるため、必ず公式情報を確認してください。
終了後は何が変わる?
- メイン → 延長:機能追加や設計変更は基本なし、セキュリティ修正が中心へ。
- 延長終了後:セキュリティ更新の提供停止。新規脆弱性に曝露され、監査・保険・取引要件で不利になるケースが増えます。ESUは“暫定策”であり、恒久策はアップグレードです。
いま取るべき実務アクション
Windows Server 2019(延長サポート中〜2029/01/09)
- 更改ロードマップを確定
ハード更改・仮想基盤更新・アプリ互換テストの順で逆算。2027年中に移行設計完了 → 2028年検証・切替が安全ライン。 - 脆弱性対策の徹底
延長期間中も月例(B)更新の適用を運用ルール化。WSUS/SCCM/Intuneでの一括配布や段階配信を確実に。 - ESUの可否をウォッチ
ESU(拡張セキュリティ更新)は、延長サポート終了後に提供される「有償の延命策」です。対象・条件は製品ごとに告知されるため、必要になった段階でMicrosoftの公式情報を確認してください。 - 後継の選定
物理→仮想集約、2022/2025 への更改、もしくはPaaS/IaaS への段階移行(ファイルサーバーの一部をクラウドへ、ADはハイブリッド等)。
Windows Server 2022(メインストリーム中〜2026/10/13)
- 新規導入は原則2022(または最新LTSC)
現行案件は2022を標準に据え、アプリ互換が許すなら最新LTSC(2025)検討も。 - メイン期間の優位性を活かす
ドライバーや新規機能対応、Azure Editionのホットパッチなど、運用性とダウンタイム最小化の恩恵がある期間に集中的に設計を固める。 - 延長フェーズに入る前の棚卸し
2026年までに役割(AD DS/DNS、ファイル、IIS、RDS、印刷等)と依存関係を棚卸し。サードパーティ製品のサポート表も要確認。
Windows Server 2016・2025との比較
Windows Server 2019・2022の「前後のバージョンはどうなるのか」「いつまで使えるのか」をわかりやすく比較表にしてみました。
| バージョン | メインストリーム終了 | 延長サポート終了 | 状況 |
|---|---|---|---|
| Windows Server 2016 | 2022年1月11日 | 2027年1月12日 | すでに延長サポート期間中 |
| Windows Server 2019 | 2024年1月9日 | 2029年1月9日 | 現在延長サポート中 |
| Windows Server 2022 | 2026年10月13日 | 2031年10月14日 | 現在メインサポート中 |
| Windows Server 2025 (開始 2024/11/01) | 2029年11月13日 | 2034年11月14日 (PT表記) | 正式リリース済み(LTSC) |
※ Windows Server は「5年メイン+5年延長」の10年間サポートが基本です。
サポート終了後に現場で本当に困ること
サポート期限を過ぎると、ただ古くなるだけではありません。実務では次のようなリスクが現実的に発生します。
- セキュリティ更新が一切出なくなる
→ 新しい脆弱性に対して無防備な状態に。ランサムウェアやゼロデイ攻撃の標的になる確率が上がります。 - 監査や取引先から指摘されるケースも増加
→ ISMS、Pマーク、金融・医療などの分野では「サポート切れOS=重大リスク」と判断されることがあります。 - メーカーやMicrosoftの技術サポート対象外になる
→ 障害が発生しても問い合わせできず、「更新してからご相談ください」と案内される場合も。 - サイバー保険や情報漏えい保険の対象外となる場合も
→ サポート切れOSを継続利用していると、事故発生時に保険金が下りないケースもあります。
クラウド・Azureとサポート期限の関係
最近では「サーバー2019を更新するなら、クラウドも検討すべき?」という声も増えています。オンプレだけでなく、Azure・ハイブリッド環境にも選択肢があります。
- Windows Server 2022 は Azure Stack HCI や Azure Arc と連携しやすい設計
- Azureに移行した場合、サポート終了後でも ESU(拡張セキュリティ更新)を自動適用できるケースがある
- ADの一部を Azure AD に移行、バックアップ・DR(災害対策)をAzureに任せる方法も可能
- すぐにクラウドへ移せない場合でも、「現状をオンプレで維持+一部をAzureへ段階移行」という構成も現実的
サーバーのサポート期限を確認する方法(PowerShellで簡単)
実際に使っているサーバーのバージョンやビルドを確認したい場合は、以下のコマンドで調べられます。
systeminfo | findstr /B /C:"OS 名" /C:"OS バージョン"または、より詳細に知りたい場合はこちら:
Get-ComputerInfo | Select-Object OsName, OsVersion, WindowsInstallDateFromRegistry※ リモート環境やADで管理している場合は、Active Directory ユーザーとコンピューター、WSUS / SCCM コンソールなどから確認する方法もあります。
よくある質問(FAQ)
Q. ESUで粘るのはアリ?
A. ESUは“移行のための延命”で、恒久策ではありません。対象・条件・価格は製品ごとに異なり、後出しの告知もあり得ます。運用・監査・法令対応を考えると、正攻法はアップグレード計画の前倒しです。
Q. Azure Arc を使うと何が楽?
A. オンプレ/他社クラウドのサーバーでも一元管理でき、対象製品であればArc経由でESU配信・課金が可能。プロダクトキーの有効化不要など運用が簡素化します(※対象製品は要確認)。Microsoft Learn
Q. 2022へ上げるメリットは?
A. 2022はメインサポート中で、長期の運用余地(〜2031年まで延長サポート)があります。新規導入やリプレースの軸にしやすいです。
実務テンプレ:計画表の雛形
- 現状把握(今月):役割/台数/仮想基盤/アプリ互換/サポート表の回収
- 設計(+2か月):更改方式(インプレース/並行新設)、DR、バックアップ、運用設計
- 検証(+4か月):テスト計画、性能・負荷、切替リハーサル
- 段階移行(+6か月):部門・サービス単位で段階切替、夜間/休日ウィンドウ運用
- 完了・最適化:旧環境停止、監査証跡、運用品質KPIの定義
ポイント:アプリ互換と監査要件(ISMS/NIST/CSA等)を先に詰めると、後工程の手戻りが減ります。
MacやWindowsでトラブルなくOfficeを使うには、常にライセンスが有効な状態であることが大切です。
「Microsoft 365 Personal」なら、Word / Excel などのデスクトップ版はもちろん、最新アップデート・1TBのOneDriveも利用できるので安心です。
[スポンサーリンク]
まとめ
- 2019は延長サポート中(〜2029/01/09):更改計画を今固める。ESUは“保険”であって“解決策”ではない。
- 2022はメインサポート中(〜2026/10/13):新規・更改は2022(or 最新LTSC)を基軸に。
- LTSCの原則(5年+5年)でロードマップを逆算。期限から逆に計画すれば迷いません。
サーバーのサポート期限は、単なる「日付」ではなく、セキュリティ・信頼性・事業継続に直結する重要な指標です。とはいえ、焦る必要はありません。必要なことは「いつまでに、何をすべきか」を把握し、少しずつ計画に落とし込むことです。
今使っている環境を見直すきっかけとして、今回のタイミングをぜひ役立ててください。
おすすめ関連記事
・2025年注目のサーバーOS:Microsoft Windows Server 2022 徹底解説